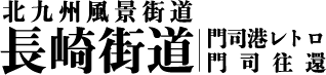小倉北区大手町1-1
小倉祇園大門町山車(県指定有形文化財)
小倉祇園の起こりは細川忠興の治世の元和4年(1618年)頃と伝えられています。
最初はそれ程賑やかなものではありませんでしたが寛永9年(1632年)小笠原氏が入部してからのち、しだいに形を整え、元禄~享保年間(1688年~1736年)にかけて都市型の祇園を成立させたと推察されます。
江戸時代の祇園は、御神幸に城下の各町内から、いろいろの趣向を凝らした山車、踊車、人形引車、傘鉾、踊り子などが隋従するという豪華なものでした。しかし、 明治時代以降しだいにこの形式が失われていき、現在みられる太鼓を主体とした祇園へと展開しました。
写真で紹介している山車も、かっては御神幸に随従していたものです。
古い小倉祇園の山車の形態を伝える貴重な資料で、現在では5基が残っています。
大門町山車のほか、3基は北九州市立自然史・歴史博物館に、1基は小倉城に保存されています。いずれも昭和38年(1963年)県の有形民俗文化財に指定されました。
(大門町山車)
明治21年(1888年)建造
昭和49年(1974年)修復 高さ4.44メートル